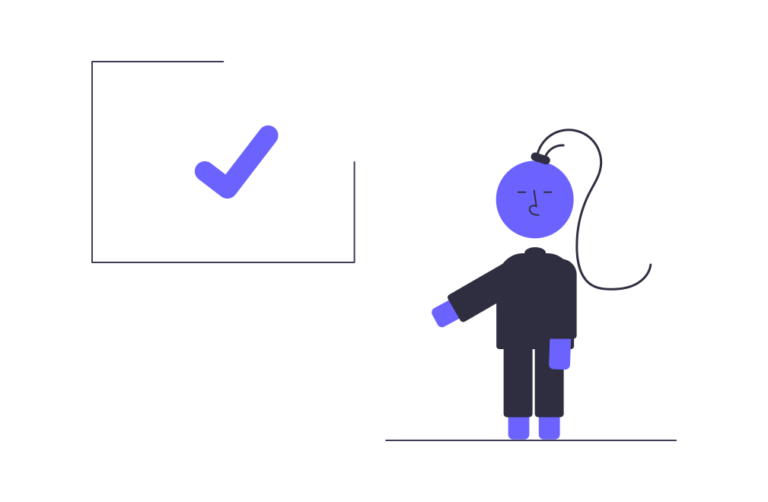コロナ禍でもほとんどのコールセンターは、変わらずに営業しています。
お客さまの在宅率が上がっているので、入電が増えているところも多いですね。
無茶な要求をしてくる人も増えてきているような気がします。
そんなお客さまに
「できません」
「無理です」
「ありません」
と、お断りをして電話を切ってもらうのは一苦労です。
この記事では、電話を切ってもらえる「お断りトーク」を解説しています。
お断り案件は、通話時間も長くなるし精神的ダメージも大きいですよね。
できるだけスムーズにお断りする方法を、見ていきましょう。
なぜ無理難題を要求してくるのか?

お客さまはどうして「できない」ことをやりたがるのか?
販売していない商品やサービスを求めるのか?
まずはここから考えてみましょう。
1.ないことを、知らない
まずは、単純に知らなかったパターン。
- プラン変更は即日適用されると思っていた。
- 交換は無料でしてくれると思っていた。
- キャンセル料はかからないと思っていた。
などなど、できると思ってたので要求してくるということです。
要求の中には、非常識なものや悪質と思われる内容も結構あります。
- 無料でやって
- すぐにやって
- 私にだけ特別にやって
こちらからしたら「いやいや、あなた常識的に考えて無理でしょ」と思う内容を平気で言ってくるお客さまの中には、確信犯の人もいますが単純に「知らなかった」という人も沢山いらっしゃいます。
「常識」、とはその人の今まで生きてきた環境や性格によって作られるので、非常識な人にとってはそれが常識になっているんですね。
このような現象は、高級商品よりも安価や無料なものに多くい傾向があり、もともとタダで提供されたものに対して交換やクレームを言うお客さまの方が実は多いのです。
2.前にやってもらったことがある
次に、「前はやってくれた」というパターンです。
これは同じサービスや商品に関してという場合もあれば、他のところではやってくれた、という場合もあり他社でやってくれたことに関しては確認のしようがありません。
前回(他社)の対応者が気を利かせたのか、そういう時代だったのか、はたまた嘘(過大表現)を言っているのか。
真相は分かりませんが、以前の体験を用いて「だから今回もやってよ」という要求です。
また、「知り合いがやってもらった」という場合もあります。
やってもらった前例があるのなら、「わたしもやってよ」という気持ちも分かります。
3.どうでもいいから、やって
「そのような商品はない」「ご要望には応えられない」と言っているのに、「そんなことはどうでもいいから、やって」というパターン。
前例や一般的には~ということはどうでもいいから、とにかく自分の要望を通したいというお客さまです。
特徴としては、
- 声が大きい
- こちらの話を聞かない
- 年配者
このような人が多いですね。
この人たちには常識や一般論、そんなことは通用しません。
対処方法フロー

無理を言ってくるお客さまの特徴は分かりましたね。
ここからは具体的にどのようにしたら要求を断ることができるのか、具体的に解説します。
1.状況ヒアリング
「〇〇をやって欲しい」これを言われた瞬間に「それは無理です」と突っぱねるのはちょっと危険です。
これはどんな内容の入電でも同じことが言えます、まずは状況をしっかりとお聞きしましょう。
相手の要求をお聞きする時のポイントは2つです。
適度な同調、共感を入れる
2.話を一旦まとめる
お客さまの話を聞いた後は、まず一旦話をまとめましょう。
相手の要望を断る前に、要望をきちんと把握することは重要なポイントです。
回答する前にしっかりと認識合わせをしておきましょう。
状況:商品が届いていたら箱に傷がついていたので、交換して欲しい
- 「お届けした商品の箱に傷があったので、交換して欲しいということですね?」
- 「お届けした商品の箱に傷がついていたので、交換ご希望ということですね?」
上記の2つ、どちらも間違いではないですが、②の方が丁寧に聞こえます。
違いはお分かりでしょうか?
「~して欲しいんですね?」という言い方は、若干上から目線であったり、お客さまが一方的に望んでいる印象を与えます。
できるできないは置いておいて、箱に傷があったんだからきれいなものに交換するべきでしょ?そちらから交換させてくださいと言ってもいいのでは?という思いに対する理解が感じられません。
なので、②の「ご希望」「ご相談」「~することはできないか」ということですね、という表現の方が中間的なニュアンスに聞こえるのでベターな言い回しです。
ほんの小さな違いですが、この辺りの言葉の選択は、後に効いてきます。
3.保留をかける
お客さまの要望をお断りする時は、即答はなるべく避けましょう。(クレームではない普通の問い合わせは除く)
オペレーターにとっては「そんなのできっこない」という案件でも、お客さまにとっては「できるかどうか調べて欲しい」という思いがあります。
調べもせずに「できない」と言われると、どうにかして欲しいという気持ちが増し、粘られることもあるのでポーズだけでもいいので、調べたり確認して差し上げましょう。
4.できないことを伝える
ここでやっと、要望に応えられないことを伝えます。
ポイントは2つ。
1つ目は「できるかどうか調べた」「個人的には何とかしてあげたいと思っている」という気持ちを表しながら伝えることです。
「お調べしたのですが、~はありませんでした」
「他にできることは無いか確認したのですが、〇〇はやはりできませんでした」
という風に、「できる方法を探してみたが、(残念ながら)無かった」というニュアンスで伝えると、一生懸命さや親身さが伝わるのでお客さまは「このオペレーターはわたしの味方なんだ」と思ってくれるのです。
クレームやお断りの電話には「お客さまの味方になる」ことが上手くいくコツ。
「できません」「わかりません」「ありません」と突っぱねて敵になってしまうと、お互い体力を使い嫌な感じで切電されてしまい、モチベーションも下がります。
もう1つのポイントは、何度か繰り返しお伝えする、ということです。
「お調べしたのですが、できませんでした」と一度伝えて「はい、そうですか、わかりました」と言ってくれれば良いのですが、「何でですか?」「他に方法は?」「別の人に代わって」と言われてしまうことも想定しておかなければなりません。
「私も何か方法は無いか調べてみたのですが、やはりございませんでした」
「〇〇はできないので、△△(代替え案)いただく方法はいかがでしょうか?」
と言ったやりとりを何度か繰り返して納得いただくのです。
場合によってはもう一度保留をかけることもあります。
話が平行線になったら、一旦保留にするのも良いでしょう。
要所要所で「お力になれず申し訳ございません」などのお詫びの言葉は忘れずに。
5.時には厳しく
何度かやり取りをして話が平行線になっり、同じ内容を何度も繰り返すようであれば少し厳しめの言葉をかける必要があります。
「先ほどから何度か申し上げておりますが」「私どもにもできることとできないことがございます」「これ以上ご案内できることはございません」
これを言ったら余計怒るのでは?と心配になりますよね。
そうです、一旦怒られたほうが良いのです。
冷静に当たり障りなく話を進めていても、着地点は見つからず時間がたつばかりです。
時には厳しめの言葉をかけ、怒られ、お詫びし、再びできない理由を伝えて~を繰り返しご納得いただくのが、遠回りなようで実は近道だったりするんですね。
ポイントは厳しめの言葉を伝える前に「4」の段階で「このオペレーターは味方だ」と思ってもらえるように、一生懸命さを伝えること。
お客さまとの距離が縮まれば、「これ以上はどうにもならない」という状況も理解してもらいやすくなります。
6.最後は丁寧に
シブシブでも、「分かりました」と言っていただけたら丁寧にお詫びを添えましょう。
ここで手を抜くと、また盛り上がってしまい初めの段階に戻ってしまします。
「お力に添えず大変申し訳ございません」
「お手数をお掛け致しますが、何とぞよろしくお願いいたします。」
としっかりと、気持ちを込めてお詫びします。
決して急いで切ろうとしないでください。
ゆっくり、ゆっくりです。
そして、最後の名乗りも丁寧にはっきりと伝えます。
名前を言わなかったり切り急ぐと「早く電話を終わらせたい」「責任を負いたくない」という印象に繋がってしまうので最後は大事です、ゆっくり丁寧に。